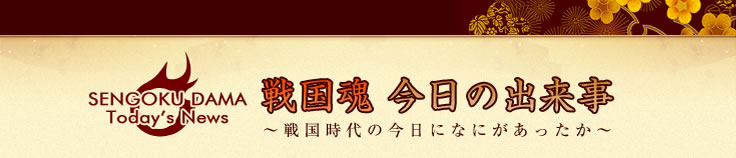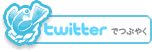■【清水宗治、秀吉の誘降を拒否】天正十年(1582)4月4日
羽柴秀吉が備中高松城主清水宗治を誘降するが宗治はこれを拒否、秀吉は岡山城に入る。
清水宗治は天文六年(1537)、備中南部の国人・清水宗則の二男として生まれました。通称を長左衛門といい、初め三村氏の被官で備中高松城(岡山市)主・石川氏に属していました。石川左衛門佐久孝の娘を娶って幸山城(岡山市)主となった宗治は、永禄八年(1565)に久孝が没すと後を嗣いで高松城主となりました。しかし鈴木・秋山氏ら備中北部の国人衆は宗治が高松城主となることに反対したため、これに対抗すべく宗治は程なく毛利氏に属します。小早川隆景の配下となった宗治は、以後毛利氏に忠実な武将として行動しました。
天正八年(1580)、織田信長は長きにわたった石山本願寺との戦いを制し、本願寺顕如は石山を退去しました。これより信長は本腰を入れて毛利氏との対決に臨み、まず手始めに羽柴秀吉に命じて宗治の調略を行わせます。秀吉は宗治に信長の朱印状を示し、味方になれば備前・備中を与えるとの破格の条件をもって誘いますが、宗治がきっぱり拒絶したため、秀吉は備中攻めを後回しにする形で因幡鳥取城(鳥取市)攻めに向かいました。
同十年、秀吉の中国攻めが開始されると、宗治は高松城に籠城しました。秀吉は侵攻に先立ち、再度勧降の使者として蜂須賀正勝・黒田官兵衛を派遣して宗治を説得しますが、やはり宗治は動じませんでした。秀吉はこの日宇喜多氏の本拠・岡山城に入り、軍備を整えます。宇喜多氏では前年二月に直家が没しており、わずか九歳の秀家が後を嗣いでいましたが、秀吉は直家の弟・忠家や戸川逵安(みちやす)以下の宇喜多軍一万に先導させて出陣、十四日から備中高松城の支城である冠山・宮路山・加茂の各城(いずれも岡山市)を攻略、やがて高松城に攻め寄せます。高松城は三方を深田に囲まれて攻めにくい地形でしたが、秀吉は黒田官兵衛の献策により水攻めを採用しました。城の周囲に長大な堤を築いて足守川の水を引き入れると、折しも雨が続くという幸運もあって城は水没、これには勇将宗治もどうしようもなく、ついに六月四日に自刃することになります。
浮き世をば今こそ渡れもののふの 名を高松の苔に残して
しかし宗治自刃の二日前、信長は既にこの世を去っていました。