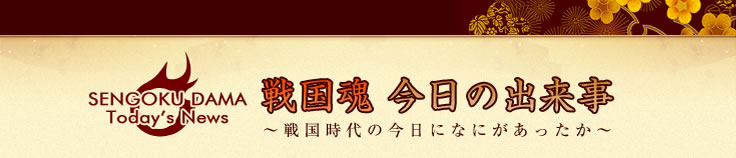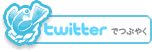■【名僧快川紹喜寂滅】天正十年(1582)4月3日
織田信長が信忠に命じ、六角義治らを匿った甲斐恵林寺を焼き討ち、住持快川紹喜は炎の中で寂滅。
名僧として知られる快川紹喜(かいせん・じょうき)は美濃土岐氏の出自といわれ、初め京都妙心寺・美濃祟福寺に住しました。弘治年間、美濃国主斎藤義龍は妙心寺第三十四世の別傳(べつでん)に深く帰依して傳燈寺を建立、永禄三年(1560)年十二月には美濃国内の禅寺をこの下に属させようとしたことから快川らと対立し、将軍義輝をも巻き込んだ混乱を招く結果となりました。その際、稲葉山城(岐阜市)下井ノ口には次のような落首が見られますが、民衆が義龍に反発していることがわかります。
類親の首を切りぬる義龍が 殺人剣を今ぞもちいる
紫野ゆかり頼めど別傳を みながら人はあわれとはみず
大海を知らぬも道理義龍は ただ井ノ口のかいる(蛙)なりける
快川は永禄七年(1564)十一月、武田信玄に招かれて甲斐・恵林寺(山梨県塩山市)に移りますが、信玄は快川を迎えるため前年に恵林寺領の一斉検地を行うほど熱心でした。以後信玄は快川に帰依して禅を学びます。快川は信玄の葬儀の際には導師を務め、天正九年(1581)九月には正親町天皇より大通智勝国師の号を特賜されるなど、名実ともに一級の名僧となりました。
翌年三月、織田信長は武田勝頼を滅ぼしますが、川尻秀隆は快川が勝頼の遺骸を無断で引き取り追善供養した、信長の仇敵であった六角承禎(義賢)の長男義治あるいは二男の大原次郎永賢らをかくまった(人名は異説あり)などとして、詰問の使者を発しました。快川が「存ぜぬ」と突っぱねると、織田勢は寺に乱入して僧たちを山門に上らせ、梯子を外した後に火を放ちました。僧たちが次々と喚きながら焼け死んでいく地獄絵図が展開される中、快川は一人騒がず結跏趺坐していましたが、その際に次のような名言を残しています。
安禅不必須山水 滅却心頭火自涼
(安禅必ずしも山水をもちいず、心頭滅却すれば火もおのずから涼し)
『甲乱記』によると、この際快川を含む八十四人の僧が焼き殺されたということです。