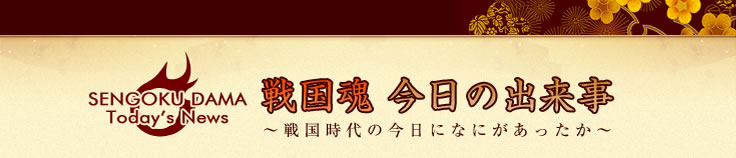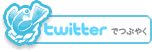■【尼子晴久が中国八ヶ国の守護に】天文二十一年(1552)4月2日
将軍足利義藤(義輝)が尼子晴久を、出雲・隠岐に加えて因幡・伯耆・備前・備中・備後・美作の守護に任じる。
尼子晴久は永正十一年(1514)二月十二日、政久の子として月山富田城(島根県安来市)に生まれました。通称三郎四郎、初め詮久(あきひさ)と名乗り、民部少輔のち修理大夫に任ぜられます。父政久が永正十五年(1518)九月、出雲阿用城(同雲南市)攻めの際に流れ矢に当たって戦死したため(没年は永正十年ともいう)、詮久は天文六年(1537)に直接祖父経久の後を嗣ぎ二十四歳で当主となり、同十年(1541)十月には将軍義晴の偏諱を受けて晴久と改名しました。(以後、本稿では晴久で統一します)
晴久が家督を嗣いだ頃尼子氏はしきりに勢力拡大を図り、東は美作・播磨にまで勢力を及ぼします。しかし西には大内氏が控えており、加えて当時大内氏の傘下にあった毛利元就が晴久にとって厄介な存在となっていました。天文九年(1540)六月には新宮党の国久が元就の居城・安芸吉田郡山城(広島県安芸高田市)を攻めますが、五龍城(同)主・宍戸元源らの強固な防戦により失敗したため、八月には晴久自身が三万の大軍を率いて再び出陣、吉田郡山城を攻囲しました。しかし元就のしぶとい籠城戦術に対して尼子軍は一枚岩とは言えず、晴久は新宮党の下野守久幸を「臆病野州」と蔑んでいたため、これに怒った久幸は翌年正月十三日、自殺に等しい戦死を遂げています。久幸の戦死は大打撃で、この時点で尼子氏の敗北は決定していました。やがて大内義隆が大軍を率いて元就救援に来着との報を受け、晴久は退陣しました。
この年の十一月に経久が没すと大内義隆は翌十一年に出雲へ侵攻、富田城を包囲します。この戦いは晴久に軍配が上がり、義隆は退却時に尼子勢の追撃を受け、養嗣子晴持を失っています。その後晴久は失地回復に努めますが同二十年九月、陶晴賢の謀反により義隆が長門深川大寧寺で自刃、大内氏は滅亡しました。
ライバルであった大内氏の滅亡の影響もあってか、この日晴久は室町幕府十三代将軍・義藤(のち義輝)から出雲・隠岐に加えて因幡・伯耆・備前・備中・備後・美作の守護に任ぜられました。しかしこれが尼子氏に咲いた最後の花で、同二十三年に晴久は軍事面を中心に家中を支えていた新宮党の粛清を行い、以後尼子氏の勢力は急速に衰えていくことになります。