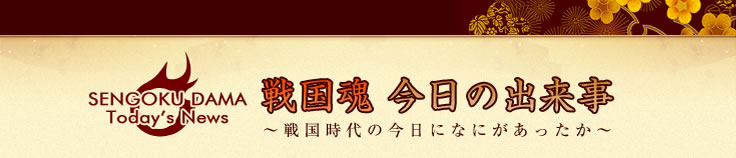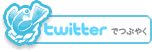■【山中城陥落】天正十八年(1590)3月29日
羽柴秀次軍が北条方の箱根山中城を数時間の戦闘で落とす。北条方松田康長・間宮康俊が戦死。また豊臣水軍は北条水軍と伊豆ヶ崎で戦う。
天下統一を目前にしていた豊臣秀吉は、北条氏政が何かと理由を付けて上洛しないことに業を煮やしていました。そんな折、真田昌幸の属城・名胡桃城(群馬県みなかみ町)が北条方に奪われるという事件が起きると、秀吉は待ってましたとばかりに北条氏討伐の兵を挙げ、この年の三月一日に大軍を率いて京都を出陣、小田原城へと向かいました。
山中城(静岡県三島市)は韮山城(同伊豆の国市)とともに小田原城(神奈川県小田原市)の西・箱根路を守る要衝で、城主の松田康長と援将の玉縄城(同鎌倉市)主・北条氏勝が固めていました。この日秀吉は韮山城へは織田信雄・蒲生氏郷らの四万四千の兵を向かわせ、山中城へは豊臣秀次を主将とする六万八千の兵(徳川家康の三万を含む)を差し向け、自身も四万の兵を率いて続きました。
秀次の先鋒を務めるのは中村一氏・山内一豊・堀尾吉晴・一柳直末・田中吉政らで、この戦いで特に活躍したのが中村一氏隊でした。一氏の家臣には「槍の勘兵衛」の異名を持つ勇将・渡辺勘兵衛がおり、勘兵衛らの活躍で山中城の南にある岱崎の出丸は一瞬のうちに落とされますが、その際の戦いで出丸の守将・間宮康俊が戦死しています。勢いに乗った一氏らは山中城三の丸へ攻め込み、大激戦が展開されました。松田康長は四千の兵を督して奮戦、秀次の将・一柳直末を討つなど頑強に抵抗しますが、二の丸の守将・北条氏勝は一戦に及ばず城から脱出、かろうじて居城の玉縄城へ逃げ戻るという有様でした。やがて三の丸・二の丸とも落とした秀次勢が本丸へ迫ると、康長は自身槍を揮って戦いますが、所詮兵力が違い過ぎました。康長もついに力尽きて戦死、結局山中城は半日で落城することになります。